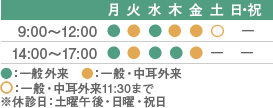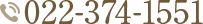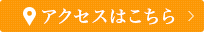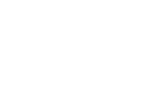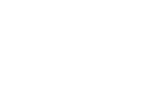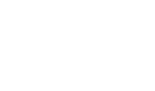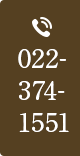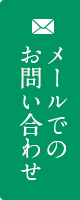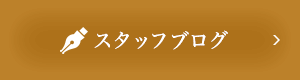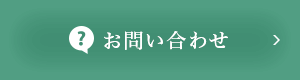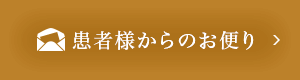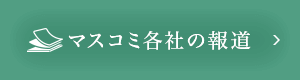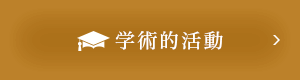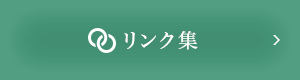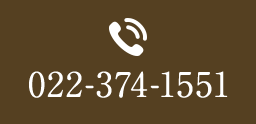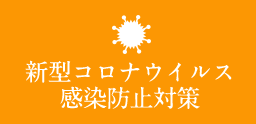第64回日耳鼻東北地方部会連合学会
日耳鼻東北地方部会連合学会は、東北各県の耳鼻咽喉科地方部会の先生方が一同に会して討論を行う学会で、各県持ち回りで毎年7月後半に行われます。若い先生方の登竜門の場としても活用されており、今年は山形市で行われ今回も研修医の先生を含め伸びしろ豊かな有望な先生方が素晴らしい発表をされ、活発な討議が行われました。
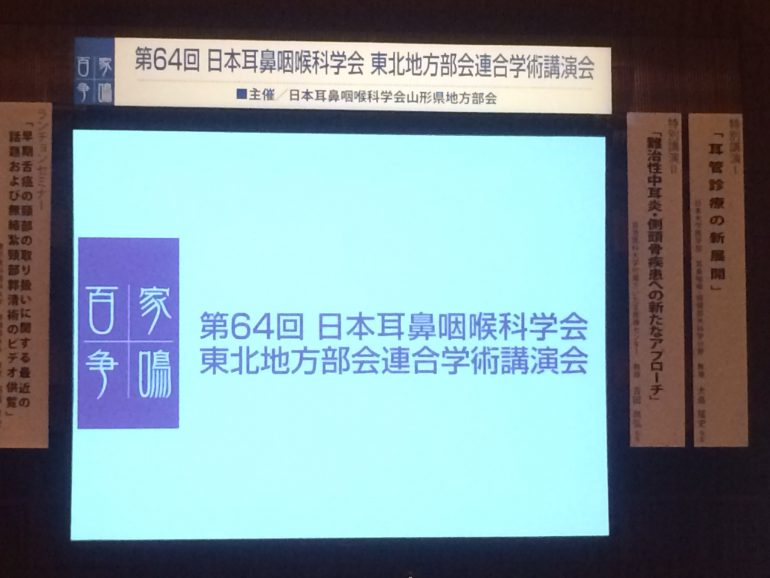
学会開始直前
第13回耳鼻咽喉科短期滞在手術研究会
耳鼻咽喉科短期滞在手術研究会は、耳鼻咽喉科領域における日帰りや短期入院での手術をいかに安全に行い、そしてその技術を発展させるかをテーマにして、年1回開催されている研究会です。このテーマに即した講演やシンポジウム、そして実際に短期滞在で手術を行っている先生方からの提案や報告などがあり、毎年活気あふれる討論が行われています。今年は大阪で行われましたが、今回はチーム医療として欠かせない看護師の方々も交えたワークショップも行われました。 術者の技術や手術適応の他に、医師以外の医療関係者を含めたチームワークが、より安全な手術を行うためには重要なポイントであることが再認識された一日でした。

特別講演中
第10回国際真珠腫および耳科手術学会 10th International Congress on Cholesteatoma and Ear Surgery
国際真珠腫学会は4年に一度開催される国際学会で、主にヨーロッパ各国が持ち回りで主催します。真珠腫性中耳炎を中心に中耳~頭蓋底手術、人工内耳手術も対象とした学会になっています。第10回となる今回は6月5日~8日まで、スコットランドのエジンバラにて開催されました。
今回は、ビデオワークショップー鼓室形成術ーというカテゴリーで鼓膜形成術接着法の口演をさせていただきました。私の他3名の先生方が鼓室形成術に関する各々の手技手法を発表され、それについての議論がなされました。自分の発表が終了すれば演台からおりるのが通常ですが、今回は正面舞台の椅子に着席しそれぞれの演者と司会者、そして聴衆の先生方を交えてのディスカッション形式でした。
やはりまだまだ英語力不足で自分の意見を正確に伝えるためのツールがなっていない状態では、国際舞台でものを言うことは難しいと痛感しました。

発表中
岩手耳鼻咽喉科臨床研究会
当院では宮城県のみならず東北各県からご紹介いただく患者様も受診されます。今回は岩手県の盛岡市で開催されました岩手県耳鼻咽喉科臨床研究会にて、当院で行われている中耳手術の概略と術後治療に関しての解説を行いました。岩手県は、日本の県の中で最大の面積を有しますが、中央に北上山地がそびえ特に沿岸部と内陸部の行き来が大変です。今回内陸部の盛岡市で講演が行われたにもかかわらず、沿岸地域の先生方も含め多数の先生方にご来場いただきました。術後問題が発生した場合の対応は手術をした施設でも難しいことがあり、ご紹介いただいている先生方にはご迷惑をおかけしておりますが、今回のような講演などによりご加療される第一線の先生方と密な連携を持つことで、多少でもその解決の糸口となることが患者様にとっても重要なことと考えています。
第59回仙台北部耳鼻咽喉科懇話会(SNORL会)
仙台北部耳鼻咽喉科懇話会(SNORL会)は、泉区を中心に仙台市北部周辺で診療されている耳鼻咽喉科の先生方で構成される勉強会です。平成6年より始まり、今回で59回となりました。この会では近隣の他科の先生のご講演を拝聴して耳鼻咽喉科領域以外の知見、そして他科の先生との交流を深めることを目的としています。毎回、当院から耳鼻咽喉科領域(特に耳科)のトピックなどを情報提供しています。他の先生方もこのような勉強会を通じて、さらなる医療水準の向上を目指しています。
ブータンでの第5回ボランティア手術
当院では現在ブータン王国でボランティアによる中耳手術を行っています。3年を1クールとして計画し、去年までの3年間に計4回約100耳の手術を行って第1クールを終了しています。過去4回とも首都のティンプーで行っていましたが、今回は2月23日~28日の6日間の日程で、パロ空港から南へ車で約5時間、インドとの国境の町プンツォリンで手術を行いました。この病院には耳鼻咽喉科医師の常勤がいないため、スタッフも含めブータン関係者全員がティンプーからプンツォリンにやってきました。初めての地方の町での活動ということで、まずは下見を兼ねて日本からは院長、副院長、看護師長の3名、そしてブータン関係者数名での活動となりましたが、結局3日間の手術日程で計23耳の手術を行っています。今回の手術では、手術器具を直接医師に手渡す介助をすべてブータン人のスタッフで行っています。また3耳の手術をブータン人医師に行ってもらいました。介助するスタッフに関しては既に大体の作業内容を把握しており、指導はほとんど不要になりました。医師に関しても、少しずつではありますが低侵襲での手術法を獲得しつつあります。この第2クールの3年で一人立ちができるよう彼らをサポートしたいと思っています。

手術室
第162回日耳鼻宮城県地方部会学術講演会参加
日耳鼻宮城県地方部会は、宮城県の耳鼻咽喉科の先生方が参加する学会で、年3回(東北地方の6地方部会が合同で開催する連合学会を含めると4回)開催されます。臨床の第一線で診療されておられる開業医の先生方も多く参加され、熱のこもった議論が展開されます。今回は、慢性穿孔性中耳炎の再手術例に対する術後経過について報告しました。もちろん手術は1回で成功することが理想ですが、現実的には術後の鼓膜再穿孔や難聴再燃により再手術をせざるを得ない例があります。今回はそのような例での術後経過について検討し報告しました。
第25回日本耳科学会総会学術講演会参加
日本耳科学会は、耳鼻咽喉科領域の中で耳の疾患を中心に診療、研究されている先生方が発表や議論をする学会です。今年は長崎大学耳鼻咽喉科の髙橋晴雄教授が会長となり、長崎ブリックホールにて開催されました。当院からは、軽症の真珠腫性中耳炎に対する新しい術式の報告、そして当院で行っている耳鏡(耳内を観察処置するときに使用する筒状の器具)内での鼓室形成術の際に行う鼓膜形成手技の改良に関する一般口演を行いました。長崎というややアクセスに難がある地での開催にもかかわらず多数の先生方が参加され、それぞれの分野で活発な議論が行われていました。
AAO-HNSF 2015
今年で9回目を数えるアメリカ耳鼻咽喉科学会(AAO-HNSF)での教育講演のために、アメリカはテキサス州ダラスへ兵庫医科大学の阪上雅史教授とともに行ってきました。例年この教育講演は聴講料が必要(前売りで50~60$)でしたが、今回は若い耳鼻咽喉科医に積極的に教育講演へ参加してもらいたいという会長の意向もあり、聴講料は無料となったようです。そのためか我々の講演にも80名近くの先生が参加され、講演後も活発な議論が行われました。講演内容もその時々でのトピックを取り入れているため、初期のころと比べかなり変更されています。最近では耳科手術に積極的に内視鏡が導入されており、我々の鼓膜形成術接着法や接着法を基礎とした鼓室形成術における内視鏡下手術も紹介しました。 来年はサンディエゴ、もし講演申請が受諾されればまた新しい内容を取り入れ紹介していきたいと思っています。

講演終了直後。
(平成27年9月29日、ダラスにて)
ブータンでの第4回ボランティア手術
ブータン王国は、人口約70万人、面積が38400平方キロ(九州とほぼ同等)の小国で、一日2ドル以下で暮らす人が国民の25%を占める後発発展途上国(いわゆる最貧国)の一つです。
3年前より年1~2回、ブータンでのボランティア中耳手術を行っています。今回は4回目で、8月30日~9月4日の6日間、当院院長および副院長の他、久留米大学上田祥久先生、そして兵庫医科大学池畑美樹先生にご同行を賜り計27耳の手術を行ってきました。ブータンへは、タイのバンコク経由で半日~1日弱かかりますので、実際の手術期間は3日間ですが準備も含め約1週間ほどの行程となります。今回は、ブータンの医師にも手術を行ってもらいましたし、手術の介助も現地のスタッフに積極的に参加していただきました。回数を追うごとに彼らの手術の知識や手術に対する姿勢に向上を認め、驚くほどの進歩です。
次クールの3年で、彼ら自身で手術を行うことができるのではないかと考えています。

手術中

病院スタッフ、参加医師、看護師と